社外メンターについて知ろう
社外メンターとは?
上司には話ずらい・・・同じ従業員同士でも、話ができない・・・そんなときに、活用を考えたいのが、「社外メンター」というサービスです。
メンター制度とは、若手社員のサポート役として、上司とは別に、先輩社員がサポートを行う制度のことです。このメンター制度を外部の人に頼もう。というのが、社外メンター制度です。
|
コンテンツ/見出し |
社外メンターのメリットとは?
同じ会社の人に、「実は、転職したいんだよね」「実は、仕事をやめようと思っているんだよね」「本当は、違う部署で働きたいんだよね・・・」
このようなデリケートな内容の場合、社内の人には、聞かれたくない・・・
という場合があります。
そこで便利なのが、「社外メンター」という制度です。
メンターが社外にいるメリットは、部下でも上司でも同僚でもないからこそ
「本音が話せる」という部分です。
もちろん、メンターがいれば良いわけでは無く、メンター自身も、「この人なら話しても大丈夫」と思ってもらう事が大事になりますね。
社内メンターが失敗する理由とは?
メンターの役割は、相手の本音を引き出し、人を導く事です。
何かを教える事ではありません。
ティーチングではなく、コーチングをする。という部分が大事になります。
直属の上司が
「今の仕事に、満足していますか?」「本当は、どうしたいですか?」と部下に聞いても
上司は評価者でもあるので、「実は・・・」の本音を言いづらいことも多々ですよね
でもそのまま不満を溜めていると、周りに愚痴や職場の悪口ふりまいたり
最悪退職、、ということにもなりかねません。
そこで活用したいのが、社外にメンターを設けるということです
メンターの役割とは?
メンターの役割は、相手の内面にある「おもい」を、外に表現させてあげる事です。
メンターが何かを教えたり、尊敬されたりする必要はありません。
メンター制度で大事なのは、「部下や相手を理解する」という部分です。
相手が心にためている「おもい」「かんがえ」を理解し、解放してあげる事が大事になります。
|
・悩みを吐き出す場所をつくる ・教えなくてよい ・相手を理解する |
それって、本当に大丈夫ですか?
仕事を任せた部下に、「大丈夫?」という言葉をかける事って、多いと思います。
任された部下は、とっさに「大丈夫です」「いま取り組んでいます」と答えたとします。
しかし、いつまで経っても頼んだ仕事が仕上がらない・・・
なんて事がありませんか?
この場合、部下は「大丈夫」と言っていますが、本当は、「大丈夫ではない」のです
はじめて仕事を任せる場合、任せきりにするといけない・・・と言われています。
なぜなら、部下はどこに時間がかかるのか?
どこがポイントになるのか?
が分からないからです。
もっと細かく分析すると、「何が分からないのか?」すら理解していない場合がほとんどです。
この場合、
「どこでつまずいているの?」
「君は、どこが重要だと感じているの?」
「何かサポートできる部分を教えてくれる?」
という部下に進捗をチェックして、方向修整をする事が大事になります。
しかし、ここでも
「大丈夫です」という部下がいます。
この場合の問題は、部下との「信頼関係のなさ」となります・・・
社内のメンターが失敗するのは、この信頼関係をつくらずに、いきなり核心的な質問をしてしまうからです。
もしくは、すぐに怒ったり、教えたりしてしまい
相手から考える時間を奪っているからです。
本音はいいずらい
社外メンターの役割は、「社内メンターでは引き出せない従業員の本音を引き出しやすくする」という部分です。
ある程度の会社になると、様々な年代の人々と一緒に仕事をする事になります。
50代の人が、20代と一緒に働くのが会社です。
しかし、よく考えてみると、これには、かなりムリがあります。
10年違っただけで、考え方には大きな違いがあります。
黒電話を使っていた時代と、スマホの時代では、コミュニケーションに対する考え方も大きく違います。
根性論で頑張ってきた昭和世代と、スマホ、webでのコミュニケーションが当たり前の若い世代では、考え方も行動も違います。
マネジメントとプレイングに年齢差がある場合
部下は
「上司に言っても、分かってくれない」
「いつのまにか、根性論になっている・・・」
上司は
「今の若手は・・・」
「俺のころなんて・・・・」
となってしまいます。これを解消するには、社外の中立な人が必要になります。
ここにきて、やっと「社外メンター」の登場です。
社外メンターは、若手とマネジメントの「橋渡し」のような役割になります。
|
・社内の人には言えない事がある ・社外の人だからこそ、言いやすい ・社内に中立な立場をつくる |
本音を話せる場所をつくる
人の悩みの大半は、「聴いてくれる人」がいたら解決します。
答えは出ていない場合でも、「解決ができます」
居酒屋で愚痴を言うのは、心理的には、正しい方法だといえます。
悩みは人と共有された時点で、半分は解決されています。ずっと心に引っかかっている状態が一番よくありません。
「本当は、違う部署で働きたいけれど、だれにも言えない・・・」
こんな状態で、だれにも相談しないでいると
「なんでもこの会社で働いているんだろ・・・」
となってしまうのが人間です。
外部メンターの大事な仕事の一つが、この「心のひっかかり」を外部に出す事なのです。
社内に「本音を出せる場所」をつくると
「ガス抜き」になります。
営業では、このガス抜きを定期的にしておかないと、うつ病になる人が増えたり、離職率が高くなります。
心には「不満」というガスがたまるのですが、誰かが「聞いてくれる」だけで、このガスが発散されて、前向きな気持ちになれます。
組織で働いているのは、一人の人間です。ロボットでないので、このような細かいケアが大事になります。
心のケアができている組織は、離職率も低く、生産性も高いといわれています。
ストレスを減らす時代へ
時代は、確実に「自然体」「リラックス」「楽しむ」というキーワードと方向に向かっています。
しかしながら、まだ「昭和型」のマネジメントに固執している会社が多いのが現状です。
命令をして、アメとムチで人を動かす。
これでは、これからの時代に、変化をしていく事ができません。
最終的に生き残るのは、「変化をやめなかった会社です」
「外部メンター」という制度も、これからの時代には、チームや会社に必要となる考えです。
日本では、まだ、「外部メンター」を取り入れている会社は少ないですが、今後、どんどんメンター制度を導入する会社が増えると予想されます。
従業員が働きやすく成長しやすい職場を作っていくには、社員の心のケアまで、考える事が大事なのではないでしょうか?
まとめ
社外メンターとは?は、いかがだったでしょうか?
メンター制度は、取り入れたけれど、ダメだった・・・という会社も多いのではないでしょうか?
メンター制度は、信頼関係をつくる。という部分が抜けた場合、ただの「会話」になってしまいます。
やり方を覚えるだけでなく、きちんと「聴く姿勢」になる。という部分が大事です。「聴く」です。「聞く」ではありません。この辺りは、コーチングを勉強していただけると、違いについて分かると思います。
ぜひ、マネジメントにコーチングや「社外メンター」の制度を取り入れて、自社の従業員が「どういった悩みを持っているか」や「今後、どうなりたいのか?」を把握してみてください。
きっと、会社がもっと楽しくなると思います。

伊藤麻依子
お問い合わせ、ご質問は「いつでも」お待ちしております
この記事を読んだ人におすすめ
この記事を読んだ人は、以下のような記事にも興味を持っています。

コーチングとは
成長している会社はなぜ、マネジメントに
コーチングを取り入れたがるのか?

頭と心の仕組みとは
潜在意識と脳の仕組みについて
あなたはどれだけ知っていますか?

部下の育成がうまくいかない
マネジメントの悩みと解決策とは
自己肯定感の高さがポイント

部下に権限を与えたのに動かない
権限で人は動かない?権限を与えるだけでは
組織はうまく行きません・・・

HSPとは何か?
日本人の1/5人がHSPという衝撃
気にしがちな人の人生戦略とは

サーバントリーダーシップとは
支配型から、支えるリーダシップへ
サーバントリーダーシップというアイデア

組織の生産性を上げるには
会社に入ると求められる「結果」
結果を出すには、結果だけを求めては...

会社の雰囲気は、売上につながっている
雰囲気のよい明るい会社は、業績がいいらしい?
なぜ、雰囲気がよい会社が伸びているのか?

社外メンターのメリットとは
社外に中立な場所をつくる
メリットや、メンターが良い理由とは?

やる気を管理するのはやめ
時代が変われば、マネジメントも変わる
新しい時代のコンセプトは「管理しない」
コーチングを取り入れてみませんか?
コーチングを取りれてみませんか?
人は自ら出した答えには、上司からの「強制」がありません。強制がなければ、モチベーションはおのずと高まります。男性は、自分で出した答えでないと、やる気を起こさない傾向にあります。たぶん思い当たるフシがあるかと思います。
「質問力」、「聴く力」を育てることで、ビジネススキル、マネジメントスキルは大きく向上します。
当社では、「聴く」を伸ばすことで、組織をより活性化するお手伝いをしております。
具体的な手法については、ぜひサービスなどを見ていただけましたら幸いです。
お問い合わせは今すぐ、下記ボタンよりお早めにお願いいたします。


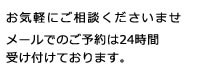









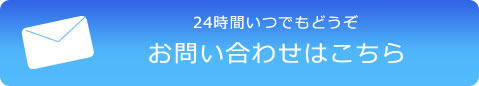

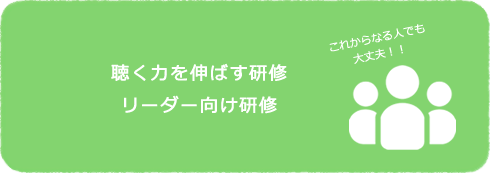
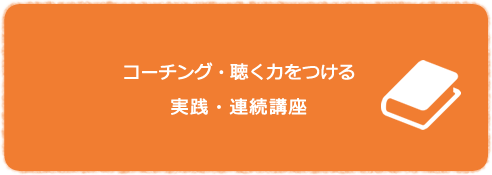


社外メンター制度をする前に、社内メンターを育てる。という方法もあります。
御社の悩みに合わせて、オリジナルのプランをおつくりします。ぜひ、ご相談くださいませ。