部下に権限を与えるとは?
部下に権限を与えたのに・・・
権限を与えても人は動かない… 報酬をあげたのに、人がついてこない・・・う〜〜・・・というお悩みをよく聞かせていただきます。頑張っているのは幹部と社長だけ・・・^^;なんて会社も、実は多いのではないでしょうか?
今回は、権限につい、心理学の面から考えてみたいと思います。
|
コンテンツ/見出し |
権限を与えたのに、動かない理由とは?
マネジメントをする場合に、してはいけない事があります。
それは、「放置」です。
現場の上司が、放置をする事と、口を出しすぎる事。これが、組織と人が動かなくなる原因となっています。
権限を与える事は必要だけれど、権限を与えた人を放置をしてはいけない。
マネジメントの難しさは、こんなところにあるようです。
放置されてしまった部下は、だんだんと「やる気」を失っていきます。
多くの人は、やる気を失ってしまうと、同時に会社や仕事に対する「意欲」が低下してしまいます。
部下にやる気がなくなってしまった場合
上司は、サポート役に回る事が必要です
子供が自分で靴下を履いているとしましょう。
「それは違う!!」
「こうやりなさい!!」
と手を出したり、口を出してしまうと・・・・
よくないと言われいます(笑
大事な経験を奪ってしまう事になるようです
先回りしてしまうと、「学ぶ」「失敗する」「成功する」というサイクルを 根こそぎ奪ってしまいます。
これでは、いつまでたっても、自立することができません。 上司は「失敗を見守る」という事が大事になります。
致命的になるのはいけませんが、小さい失敗を繰り返す事で人は成長していきます。
責任はすべて、権限を与えた上司がとり、部下には失敗する権利を与えてあげましょう。
相談しやすい雰囲気を作る
失敗の原因として多いのが、報告をしなかった・・・・という事です。
相談しずらい上司には、情報が集まってきません。 正しいマネジメントを行うには、良い情報と同じくらい、悪い情報が必要になります。 悪い情報が集まらない場合、後で致命的なミスに繋がっていきます。
「報告」は企業を管理する上で、とても大切です。
営業が終わった後に、日報を書いている企業は多いとおもいます。
しかし、毎日の日報に、すべて返信を書いている上司は少ないのではないでしょうか?
「報告」は部下にとって、かなり手間がかかる作業です
それにも関わらず、フィードバックはなかったりします...
「報告しても、返信がない...」
こんな事が続いてしまうと、会社としての風通しが、どんどん悪くなっていきます。
「どうせ、やっても意味がない...」と思われてしまうと
「報告」の質も下がっていきます。
それが続くと、不祥事に発展してしまう.. なんて事になります。
「食品偽装」の問題などは、上司に相談ができないため起きた事件とも言えます。
大した事がない、バレないと思い、放置をすると、大事なブランドイメージに傷がついてしまいます。
さらに、SNS時代は匿名で暴露されてしまう。というリスクがあります。
企業は、コンプライアンス意識を高める事も、大事になっています。
雪印と検索すると「食中毒」と関連ワードに出てきます。 Web時代のブランディングは、品質管理も含まれています
|
・風通しをよくする ・悪い情報ほど集まるようにする ・悪い情報の方が大事 |
飛行機を飛ばすつもりで
飛行機の現場などは、非常に参考になります。 飛行機は時間との戦いです。 旅客機が着陸してから次に出発するまでの時間は、国際線で約2時間、国内線の場合はわずか45分~1時間 と言われています。
短い時間で、ミスなく飛行機を飛ばすためには、日々の点検と、整備が欠かせません。
最新の旅客機は、上空を飛行中に、自機の状態を地上に送信する機能を備えるようになっています。
もはや、整備する前に、異常がチェックできるようになっています。 情報共有を徹底するとは、この事ではないでしょうか? 上司としてやる事は、情報を集める仕組みを作り、改善する事です。
悪い報告は、早めに潰す事が大切です。 そのためには、悪い情報が集まるような仕組みを作る必要があります。
ウォルマートの創業者は、毎日お客様の声、とりわけ悪い声をチェックし できる事から順番に、改善をしていったという逸話があります。
なぜ人は放置すると怠けるのか?
マネジメントをする時には、性善説と性悪説があります。
人を管理やマネジメントする場合、性善説でやる方が「マネジメントコストが低い」と言われています。 人を疑う場合は、監視カメラをつけたり、チェックを二重にしたりと、人件費以外にも、何かとコストがかかってきます。
だからといって、性善説だけで、人を信じていたら「脱税がおきた」「お金を使いこまれてしまった・・・」という事がおきたりしてしまいます・・・
人を放置してはいけない・・・というのは、よく知られた話です。色々な問題が出てしまうので、実際には性善説だけで会社を運営している人は少ないのでは?と思います。
もし性善説のみで会社が回るのであれば、人事部がある理由が説明つきません(笑 人間は、定期的にチェックをして、フィードバックをしてあげる事で やる気を維持することができます。
つまり、放置をすると、無意識的に「サボる」という行動をとってしまいます・・・
|
・放置=モチベーションダウンになる |
情報を同じにする?
権限を与える場合は、部下と上司で情報を同じにする事が大事です。 たとえば、「魚力」さんという魚を小売りしている会社では、職人さんが部下を育てない・・・という悩みを抱えていました。
なぜ、そのような事が起こるのか?というと、職人さんは、包丁の技術を若手に教えてしまうと、若手がすぐに出来るようになってしまいます。
すると、管理職の人はこう考えます「人件費が安い、若手だけでよくないか?」
これでは、職人さんは、たまったものではありません・・・
職人の世界で、「盗んで覚えろ」というのは、このような背景があり、教えた職人が損をしてしまう暗黙のルールが存在していました。
魚力さんでは、これをうまく解決して、会社の業績を大きく伸ばしました。
その方法は、人を育てた人がきちんと評価される仕組みを作ったことです。これにより、上司と部下の情報量、ノウハウの量が同じになり、人が育つようになりました。
自分が持っている情報と、部下が持っている情報を同じにすることを心がけましょう。こうする事で、上司は戦略が立てやすく、部下は戦術に集中する事ができます。
もし情報量が同じであれば、あとは「オペレーションの質」の問題になってきます。
オペレーションの差は、情報の差か、経験の差です。 経験の差は、失敗と成功の数に比例します。
任せるが放置はしないバランス感
任せているのに、なぜ、人は行動に移らないのでしょうか?心理学的な立ち場から考えてみましょう。
放置すると怠けるのは、人間の性質と言われています。
人間は、「楽をしたい」という欲求を満たすために、行動をします。
洗濯機ができたのも、掃除機ができたのも、「もっと楽をしたい・・・」どうにかならないの?」という不満を解消をするためです。
もし洗濯機がなかったらどうでしょうか?
「水をくんできて、洗濯板でゴシゴシごしごし・・・」
いったい、いつになったら終わるんだ・・・明日もこれをやるのか・・・と気がめいってしまいます^^;
洗濯機、炊飯器、冷蔵庫、掃除機、これらは、「もっと楽をしたい!!」という欲求により、生まれた製品です。
人間には、このように「楽をしたい」「頑張りたくない」という基本的な欲求があります。
仕事では、この欲求を抑える事必要になります。
人間は、だれしも、本能的に「楽をしたい」「頑張りたくない」のです。
そのような人を働かせるために有効な手段が、「放置をしない」=「話を聞く」=「悩み事を聴く」なのです。
たいていの人は、尊敬している上司から声をかけられたら、やる気が出ます。
上司から
「どうしたの?」
「何か悩んでいるの?」
「何かサポート出来る事はある?」
と、優しく聞かれたら、
「この人は、自分をちゃんと見ていてくれている」
「この人は、自分を気に留めてくれている」
となります。
このように、部下にカウンセリングを行うように、質問をするだけで、実は人のやる気は回復します。
「褒められる」事、「かまってもらう」事で、やる気を出す事ができるのです。
つまり、目にかける事が大事なのです。
人間関係の質を改善する
人間関係の質は、幸福度に比例するといわれています。
アメリカで、老人になり、死ぬ間際に「幸せだった」と答えた人を調査した、研究があります。
「わたしは幸せな人生だった」と答えた人には、ある共通した部分がありました。
人生の最後に、幸せだと答えた人は、
「わたしは、人に恵まれた」
「人間関係がよかった」
と、お金や地位についての答えよりも、はるかに人間関係が良かったと答える人が多かったようです。
人の幸せは、人が作る
人を幸せにできるのは、自分ではない他者
なのかもしれません。
ここで、少し考えてみてください。
転職の理由で一番多い理由はなんでしょうか?
「お金が少ないから」
「自分がやりたい仕事ができていないから・・・」
「会社が、家から遠いから(笑」
一番多い原因は、「職場の人間関係」のようです。
仕事ができて、あきらかに転職したら年収が上がる人がいます。
しかし転職しない。
理由をきくと、たいていは
「今の職場に満足している」と言います。
そして、よく聞いてみると、
「いまの人間関係がここちよい!!」と言います。
このように、人間関係、その時に感じる「感情」というのは、とても重要なファクターになります。
人は理性でモノを考え、感情で決断をしている
と言われています。
仕事がうまくいくか?失敗するのか?の大きな理由もここにあります。
組織がうまく行っていない場合、上司と部下の関係性を改善する事で、大きく改善する事ができます。
「合宿」をしたりするのも、昔の会社に「社員旅行」が多かったのも、コミュニケーショの質が売上と比例する事を知っていたからです。
相手のことを知るほどに、相手の事が好きになり、許せるようになります。
腹を割って話す事が大事なのは、相手と情報だけでなく、「感情」を共有できるからです。自分の悲しさや、将来の方向性を共有する事で、「感情の揺らぎ」が発生します。
この「感情の揺らぎ」が発生すると、相手を許し、共感する能力が高まるといわれています。
コミュニケーションは、ふだん何気なく行っている行為ですが、コミュニケーションが与える影響を、多くの人は意識していません。
マネジメントを行う場合、コミュニケーションや感情に注目するだけで、結果が大きく変わってきます。
もし権限で人が動かない場合は、ぜひ、自分のとっている行動を見直すようにしてください。
ティーチングからカウンセリングに変更するだけでも、大きな変化が出るはずです。

伊藤麻依子
「コミュニケーションの質」を高めるのにコーチングや1on1を取りれてみませんか?
お問い合わせは今すぐご相談くださいませ。
この記事を読んだ人におすすめ
この記事を読んだ人は、以下のような記事にも興味を持っています。

サーバントリーダーシップとは
支配型から、支えるリーダシップへ
サーバントリーダーシップというアイデア

やる気を管理するのはダメ?
時代が変われば、マネジメントも変わる
新しい時代のコンセプトは「管理しない」

コーチングとティーチングの違いとは
生産性が一気にあがる、マネジメントのコツ
部下をやる気にさせる方法とは?

社員が辞めない組織とは
優秀な人からやめていく、中間層がやめてしまう
社員が辞めない仕組みをつくるには

部下がいう事を聞きません
部下が思った通りに動いてくれません
どうしたらいいでしょうか?

部下に権限を与えたのに動かない
権限で人は動かない?権限を与えるだけでは
組織はうまく行きません・・・

マネジメントの未来を考えてみた
時代が変われば、働き方も変わって当然
これからのマネジメントに必要な事とは?

マネジメントでとっても大事な面談
グループ面談と個別面談、どちらが良いのか?
メリットとデメリットをご紹介

部下に権限を与える
部下を育てるにはどうしたらいいのか?
権限移譲しても、人が動かない理由とは
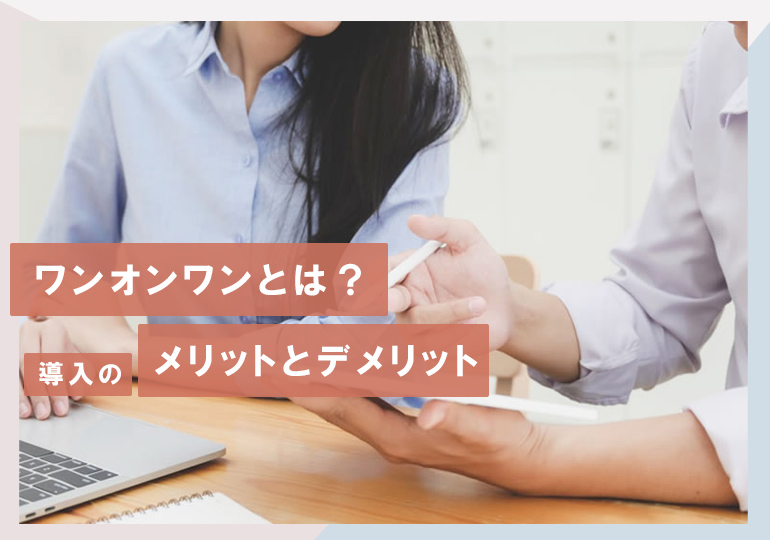
1on1(ワンオンワン)とは
ヤフーやグーグルのマネジメントで
取り入れられているワンオンワンその効果とは
コーチングを取り入れてみませんか?
コーチングを取りれてみませんか?
人は自ら出した答えには、上司からの「強制」がありません。強制がなければ、モチベーションはおのずと高まります。男性は、自分で出した答えでないと、やる気を起こさない傾向にあります。たぶん思い当たるフシがあるかと思います。
「質問力」、「聴く力」を育てることで、ビジネススキル、マネジメントスキルは大きく向上します。
当社では、「聴く」を伸ばすことで、組織をより活性化するお手伝いをしております。
具体的な手法については、ぜひサービスなどを見ていただけましたら幸いです。
お問い合わせは今すぐ、下記ボタンよりお早めにお願いいたします。


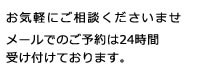







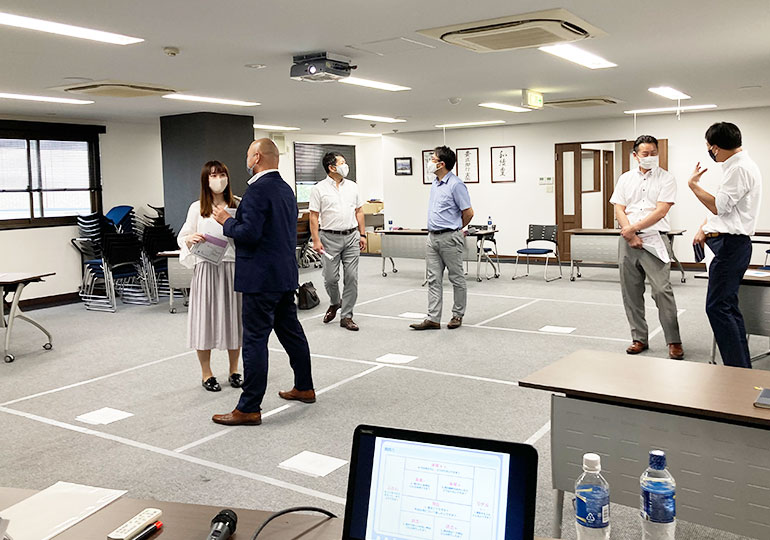
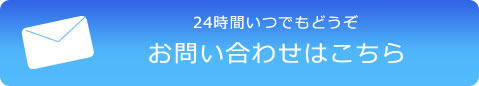

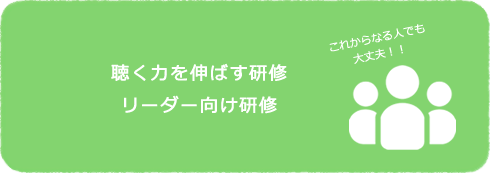
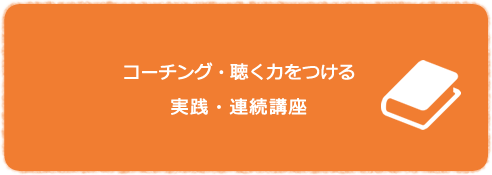


最後までご覧いただき、ありがとうございました
コミュニケーションの質に注目をすると、結果が大きく変わるかと思います。
ぜひ理論を学び、実際の現場で活かしてください^^