部下の育成がうまく行かない原因とは?
部下の育成がうまく行かない原因とは?
「部下をどう育てたら良いのか分からない」。 若手、ベテランに限らずリーダーにはこうした悩みがつきものです。
今回は、部下の育て方でお悩みの方に向けた記事です。
|
コンテンツ/見出し |
信頼されていないのでは・・・
こんな言葉が頭をよぎったことはありませんか?
自分は部下から信頼されてないのでは・・・
こんな気持ちになった時は、苦しいですよね。
相手に心をひらけない時
信頼しづらいのが人間だと思います。
信頼されないのには理由があります。
それは、日頃の「上司」の行動です。
難しいのは、人間には「合う人」と「合わない人」がいる事です。
どんなに優秀なマネージャーでも、全ての部下と気が合う。
なんて事は難しいですよね。
実は
部下に信頼されやすいか?信頼されずらいか?は
自分の内面と関係があります。
自分の内面に向き合う
すぐに怒ってしまう。
できないところばかり見てしまう・・・
欠点ばかりを指摘してしまう人には
ある原因があります
これらは全て、「自分の内面の問題」です。
信頼関係を破壊するのは、「指摘」「批判」です。
できている部分を評価しないで、指摘だけすると、信頼関係にヒビが入ります。
「そんな事はない」
と思った人は、自分が思っている以上に
周りの人は、あなたの事を信頼しています^^
尊敬されている人からの指摘は「アドバイス」に聞こえます。
しかし
嫌いな人から言われた言葉は
「批判」と捉えてしまうのが、人間の真理です。
転職理由の多くは、「上司と合わないこと」がほとんどです^^;
人間関係は、個人のモチベーションだけでなく、人生の生き方に直結します。
幸せな人を観察すると、「自己肯定感」が高いことが多いです。
マネジメントする人は2種類に分かれます。
|
1.自己肯定感が低い人 2.自己肯定感が高い人 |
この2パターンです。
自己肯定感が低い人の特徴とは?
特に、人の欠点ばかり指摘する人は、「努力して今の地位を築いた人」ではないでしょうか?
自己肯定感の低さを補うために、人よりも努力をしています。
このような人は、マネージャーになると、部下にも厳しくなります^^;
「自分だって、出来るのだから、この程度、できて当たり前だ」
できて当たり前になっています・・・
そして、基準が自分になっています。
特に自己肯定感が低いと「完璧主義」になります。すると、できている
部分よりも、出来ていない部分を指摘してしまうわけです。
自己肯定感が高い人は
逆に、自己肯定感が高い人は、人の良い部分をみるクセがついています。
自己肯定感の他に、自己信頼感、自己決定感が高いので、仕事や人生も、自分で決めた事として、前向きに生きています。
このような人は、相手の良い部分を見て、相手のペースに合わせた目標を設定できます。
「O O君は、こんな良いところがあるね」
「きっと、ここを改善したら、もっと良さが光ると思うけど、O O
君はどう思う?」
というように、面談一つとっても、相手をやる気にさせ、相手の意見をきちんと聞けます。
この自己肯定感の高いタイプは、マネジメントに向いた人と言えます。
ただ、数字にこだわる事に少し弱い傾向があるので、数値をサポートしてくれる部下を周りに配置すると上手くいきます。
マネジメントとは何か?
マネジメントは、人を動かして、結果を出すことではないでしょうか?
プレイングマネージャーの場合、自分も動いているので、マネジメントが何であるか?については、理解がしづらい部分があります。
組織がうまく回っていると、個人の成果が掛け算になります。
足し算や引き算になってしまうのは、マネジメントが上手く機能していないからです。
組織がチームとして機能するためには、マネージャーが個人の目標、計画を適切にたて、人を動かす必要があります。
そして、人を動かすには「質の良いコミュニケーション」が必要になります。
つまり、マネジメントも問題とは
いかに部下と「コミュ二ケーション」を取るか?という部分が本質になります。
日本はコミュニケーションが「空気を読む」という文化で成り立ってきました。
しかし、空気を読み合っていては、本音は出てきません。
新しい産業は生まれてきません。
新商品や新サービスをつくるには、チームの信頼感を高めて、アイデアを出し合う必要があります。
空気を読み合うのをやめ、きちんとコミュニケーションのスキルを学ぶ事は、マネジメントを円滑にしてくれます。何事も、心が一番大事ですが、まずは「型」から入る。
実は、マネジメントにはいろいろな「型」があります。
個人面談で使われる、コーチングの技術などは、応用範囲が広く、すごく役に立ち、効果がわかりやすいです。
困ったらコーチングを取り入れてみませんか?
今の育成方法やマネジメントに限界を感じたら、他社で勉強をしてみる。というのも一つの方法です。
サウンドボックスでは、マネジメント向けのコーチングの技術を教えております。コミュニケーションの質を改善する事で、「楽しく働く」を最終目標にしています。
仕事は真剣に行うものですが、真剣すぎてミスを恐れ、何もしない文化ができてしまっては意味がありません。
減点主義の人事だと、ミスを恐れ、動かない文化が出来てしまいます。
これからの時代は、減点主義でなく、加点主義で人を評価する時代ではないでしょか?

伊藤麻依子
お問い合わせ、質問はいつでも、下記ボタンよりお願いいたします
この記事を読んだ人におすすめ
この記事を読んだ人は、以下のような記事にも興味を持っています。

サーバントリーダーシップとは
支配型から、支えるリーダシップへ
サーバントリーダーシップというアイデア

やる気を管理するのはダメ?
時代が変われば、マネジメントも変わる
新しい時代のコンセプトは「管理しない」

コーチングとティーチングの違いとは
生産性が一気にあがる、マネジメントのコツ
部下をやる気にさせる方法とは?

社員が辞めない組織とは
優秀な人からやめていく、中間層がやめてしまう
社員が辞めない仕組みをつくるには

部下がいう事を聞きません
部下が思った通りに動いてくれません
どうしたらいいでしょうか?

部下に権限を与えたのに動かない
権限で人は動かない?権限を与えるだけでは
組織はうまく行きません・・・

マネジメントの未来を考えてみた
時代が変われば、働き方も変わって当然
これからのマネジメントに必要な事とは?

マネジメントでとっても大事な面談
グループ面談と個別面談、どちらが良いのか?
メリットとデメリットをご紹介

部下に権限を与える
部下を育てるにはどうしたらいいのか?
権限移譲しても、人が動かない理由とは
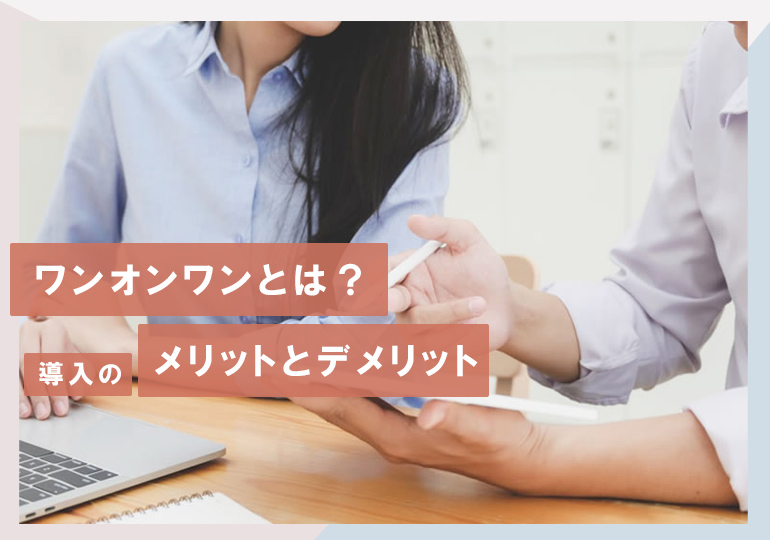
1on1(ワンオンワン)とは
ヤフーやグーグルのマネジメントで
取り入れられているワンオンワンその効果とは
コーチングを取り入れてみませんか?
コーチングを取りれてみませんか?
人は自ら出した答えには、上司からの「強制」がありません。強制がなければ、モチベーションはおのずと高まります。男性は、自分で出した答えでないと、やる気を起こさない傾向にあります。たぶん思い当たるフシがあるかと思います。
「質問力」、「聴く力」を育てることで、ビジネススキル、マネジメントスキルは大きく向上します。
当社では、「聴く」を伸ばすことで、組織をより活性化するお手伝いをしております。
具体的な手法については、ぜひサービスなどを見ていただけましたら幸いです。
お問い合わせは今すぐ、下記ボタンよりお早めにお願いいたします。


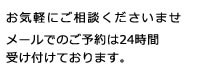








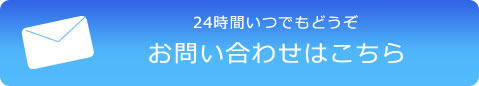

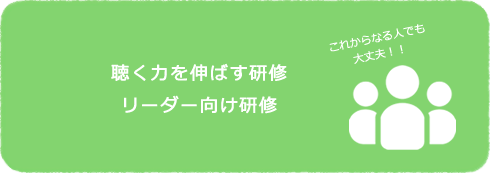
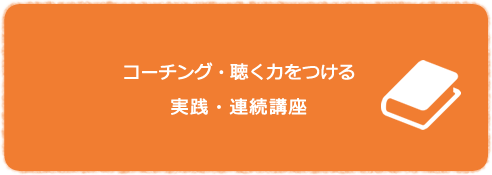


目に見えない「やる気」「共感」を高めることが、組織の生産性に直結してきます。
当社では、組織のコミュニケーションの質を改善することで、生産性を上げるお手伝いをしております。